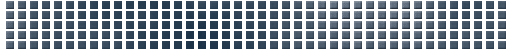
82.誰がために音は鳴る
2007.4.14
| オーケストラと吹奏楽との違いについて、別の角度から見て気が付いたことがあります。それは、作曲者の態度というか、姿勢と言ったものです。 オーケストラ作曲家が、どんなことを考えながら作曲しているかは、想像するしかありませんが、その曲を誰が演奏するかということについては、通常はプロのオーケストラであったり、音大の課題であれば学生オーケストラであったり、演奏に関して一定以上のレヴェルを持った人たちであると考えているでしょう。ですから、一般的な奏法上の難易度については特に問題にすることなく作曲することが出来ます。まぁ、新しい奏法を発明して、それを理解してもらうのが大変とかはあるでしょうけれど。作曲者は自身の芸術性を追及することが出来るわけです。 そうすると、必要でない音は書かないということも、当然のことになります。これはどういうことかというと、ある曲において非常に暇なパートがあっても不思議ではないということです。 有名な例では、ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」のチューバです。40分を超える曲の中で、第2楽章にわずか9小節しか出番がありません。演奏ステージを見ていれば分かるとおり、あのカッコイイ第4楽章は座ったまま何もしません。(これについては、佐伯茂樹著「名曲の「常識」「非常識」」で、理由が考察されています。) また、ムソルグスキー(ラヴェル編)の「展覧会の絵」のユーフォニアム。第4曲「ヴィドロ」でメロディーを吹いてお終い。(実は、こちらも楽譜上はチューバの指定ですが、音域の関係でユーフォニアムで演奏することが通例となってしまったものです。) 昨年の芥川作曲賞の選考時ディスカッションで、ある作品について「終盤で楽譜の空白を埋めるように(不要な)音符を重ねてしまったのは残念。」というコメントも聞かれました。 オーケストラ曲においては、暇なパートがあっても不思議ではないということなのです。 一方の吹奏楽では、どうでしょうか。演奏する吹奏楽団のほとんどがアマチュア、しかもスクールバンドが大多数というのが実情です。作曲家は、これを念頭に置かないわけにはいきません。すると、出てくるのが芸術性の追求と同時に教育的配慮というヤツです。それぞれの奏者が音楽を楽しめるようにという。 吹奏楽誌の投書欄に時々見かけるのが「○○という曲の××パートは、休みが多くてつまらない。部活をやめたいです。」といったようなもの。作曲家の意図なのですから休符も曲のうち、なのですけれど。私自身も、譜面をもらって吹くところが少ないと(いい曲だと思っていても)つまらないと思ってしまうことがありますからね。学生、生徒さんが一生懸命やろうとする部活で、休符が多いとつまらないと思うのも無理はありません。 かくして、つまらないパートを減らすために音符は書き込まれ、吹奏楽曲の音は厚く、重く、うるさくなって行くわけです。作曲者にとって非常に悩む部分でしょう。すべての曲がそうだというわけではありませんが。 ちょっと話が逸れますが、だからといって、オーケストラ曲が良くて吹奏楽曲が悪いと言っているわけではありません。吹奏楽曲を演奏する場合には、こういった面に注意する必要があるということです。 ただ、やはり吹奏楽の譜面を書く場合にはこういう呪縛があって、私自身も#3で書いたように音を重ねたくなってしまいます。実際に演奏や練習している場面を思い浮かべると、せっかく忙しい中集まってきたメンバーがだた座っているというのは、忍びないものがあります。 しかしなから先ほど編曲を終えた「田園」では、ちょっと考えが変わってきました(というか開き直ってきた)。 「田園」は繊細な部分が多く、また第4楽章のような音が分厚い部分もあり、そのコントラストが素晴らしい曲でもあるため、無駄に音を重ねてしまうのは「田園」の面白さを半減させてしまうことが、ひしひしと感じられるのです。ということで、楽章によってはかなり暇なパートがあります。演奏するときには、パートを演奏することよりも「田園」という音楽を作っているということを意識していただいて、休符を演奏していただきたいと、思う次第であります。 |
前を読む 『休むに似たり』TOP 次を読む
Copyright(C)2005-7 T.Miyazawa All Rights Reserved.