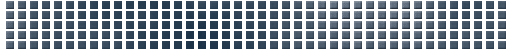
102.ひゃくに
2007.9.1
| 102(ひゃくに)と聞くと思い出すのがあのコンサート。すでに「裏べー全編」(ブログ)には書いてしまっているのですが、もう一度書いてみます。(ネタの使いまわしでスミマセン) 書くに当たっては、実名は伏せようかなと思いましたが、そのようにブログにも書いてしまっているし、別の記事(あるある失敗談#19)でも実名で書いているので、実名で書くことにしましょう。 2006年12月13日の東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団「第204回定期演奏会」 。曲目はモーツァルトのピアノ協奏曲第25番とマーラーの交響曲第6番。指揮は飯守泰次郎さん、ピアノ独奏は高橋アキさん。 この二曲の共通点は同主調への転調(例えばハ長調からハ短調へ)が特徴的なことです。そういう意味のある選曲な訳ですが、どうしてもモーツァルトのピアノ協奏曲25番は耳に馴染んだ曲というわけにはいかず、聴いている最中に退屈になってしまったわけです。 異変は第2楽章で起こりました。ホルンとフルートがメロディーに対して合いの手を入れる部分だったのですが、その合いの手が妙なのです。音楽的に合っていないように聴こえるのです。「あれ、もしかしたら、見失ったのかな?」と思っていると、指揮者の飯守さんがスコアのページを前後にめくって何かを探しているようなのです。もちろん演奏中です。その間、ホルン奏者とフルート奏者は演奏を止めてしまったようです。 しばらくして飯守さんが、 「ひゃくに、ひゃくに、、」 と、小声で言っているのです。「ひゃくに(102)」というのは譜面に書かれている練習番号(小節番号)のことでしょう。このとき私が聴いていた席はオーケストラの背後のパイプオルガン席。つまり指揮者の正面でした。指揮者の様子が良く分かるという。 演奏中ですので大声や長々と話すわけにもいかず、曲を止めるほどの大事故でもなく、致し方ないところでしょう。 曲はしばらく進んで、「ここが102」というところで飯守さんがハッキリ振り、ホルンとフルートは無事、曲に復帰したのでした。ただ、残念なことに間もなく第2楽章は終わってしまいましたが。 第3楽章は何の問題もなく終わり、楽員の皆さんは何事もなかったようにステージ袖に引けて行きました。 (その代わりといってはなんですが、マーラーの方は大変な熱演で素晴らしいものでした。) これを見て思ったのが、「プロでも馴染みのない曲は、練習時間が十分でないのだな。」ということです。一回のコンサートの練習時間が同じだとしても、演奏回数が多い曲は練習時間が累積していきますからね。しかし、現代曲ばかりのコンサートなどはどうしているのでしょうか。いつもよりは多目にやるのでしょうかね。 こんなこともありました。 2006年7月29日のフェスタ サマーミューザ2006での東京都交響楽団。指揮は佐渡裕さん。曲はハイドンの交響曲第48番とストラヴィンスキーの「春の祭典」。コンサートの前に、公開リハーサルでのこと。 「春の祭典」の「春のロンド」終盤(練習番号54)、ピッコロとフルートが早く鋭いフレーズを吹くのですが、このタイミングか合わないのです。ピッコロが遅れている感じ。二回ほどやってずれたままだったのですが、佐渡さんは心配していなかったのか、その場では特にさらうことはしなかったのです。「このまま本番をやってうまくいくのかな?」と思っていましたが、リハーサルを終えようとしたときにコンサートマスターが佐渡さんのところへ行き、二言三言言ったのですね。そしてこの部分をやり直したのです。今度はタイミングをつかめたのかバッチリでした。もちろん本番も問題なし。 しかし、本番直前までこんな事ってあるんですねぇ。 本番での演奏では何が起こるか分からないところがあります。練習が不十分であればなおさらです。プロは経験もテクニックもありますから、リカヴァリーも出来るでしょう。私たちアマチュアの場合は、練習をしっかりして不安を少なくしておくことが大事でしょう。常にそう心がけたいものです。 |
前を読む 『休むに似たり』TOP 次を読む
Copyright(C)2005-7 T.Miyazawa All Rights Reserved.